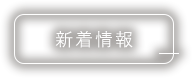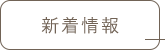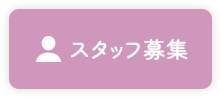大腸がんの初期症状
 大腸がんは、早期にはほとんど自覚症状はありません。やや進行してくると、血便、便秘、下痢、残便感、腹部膨満感、腹痛といった症状が現れてくることもありますが、かなり進行するまで症状が現れないこともあります。大腸がんを早期のうちに確実に発見できるのは、大腸カメラ検査のみです。
大腸がんは、早期にはほとんど自覚症状はありません。やや進行してくると、血便、便秘、下痢、残便感、腹部膨満感、腹痛といった症状が現れてくることもありますが、かなり進行するまで症状が現れないこともあります。大腸がんを早期のうちに確実に発見できるのは、大腸カメラ検査のみです。
大腸がんの症状
(進行した場合)
大腸がんが進行してくると、もろいがん細胞と便がこすれることによって、出血して起こる血便の症状や、腸管が増殖したがんによって狭くなることで、便通や腹部の不快な症状が現れるようになります。主な症状は以下の通りです。
-
血便
-
残便感
-
急に便が細くなる
-
便秘・下痢を交互に繰り返す
-
腹痛
-
腹部の張り
-
出血による貧血
-
体重減少
など
大腸がんについて
大腸がんは、大腸粘膜が何かしらの原因でがん化するものです。
大腸粘膜からそのままがん化することもあるのですが、多くは、大腸に発生するポリープを長年放置することによってがん化したものです。
日本の統計では、2019年の調査で男女ともに2位に位置し、男女計では1位となっています。
以前は胃がんが日本では常に上位だったのですが、近年は大腸がんが増加傾向にあります。
大腸がんの原因
大腸がんは、食生活を含む生活習慣と大きく関係があると考えられています。とくに食生活では、高脂質、低食物繊維といった欧米型の食生活が大きなリスク要因となることがわかっています。その他の生活習慣としては、運動不足、喫煙、過度の飲酒、肥満などが挙げられます。
また、血縁の家族に大腸がんや大腸ポリープの罹患者がいる場合、発症の確率が上昇することから、環境的要因と遺伝的要因が関わっていると考えられています。
大腸ポリープと
大腸がん

大腸粘膜から直接がんが発症するケースもありますが、多くの場合、大腸がんは大腸ポリープが放置されることによって、一定の確率でがん化して発症します。
大腸ポリープには腫瘍性のポリープと非腫瘍性のポリープがありますが、このうち、腫瘍性の腺腫や鋸歯状病変(sessile serrated adenoma/polyp;SSA/P)ががん化しやすいものとなっています。
非腫瘍性のポリープには過形成ポリープがあり,がん化の危険性のない病変とされています。
過形成ポリープとSSA/Pは基本的に形態が一緒で,不規則な核腫大や構造の不整を伴うものがSSA/Pです。SSA/Pはがん化の危険性のある病変であり、治療が必要ですが、非腫瘍性の過形成ポリープと内視鏡的に見分けることが大変困難です。大腸カメラ検査で腫瘍性ポリープやSSA/Pを発見した場合、切除しておくことで、将来のがん化の予防になります。当院でも大腸カメラ検査の際に発見したポリープは日帰り手術での切除に対応しています。
大腸がんの検査
便潜血検査
定期健診などでも行われる、もっとも基本的な大腸がんのスクリーニング検査で、便中に目に見えないほどの血液が混ざっていないかを分析装置を用いて確認します。
ただし、大腸がんで出血が多いのは、直腸近辺にあって硬い便がこすれるようなケースで、盲腸や上行結腸など小腸よりの部分ではまだ便に水分が多く、出血することはあまりありません。大腸がん患者の8割がこの検査にて陽性となりますが、2割の方は陰性と判定されてしまいます。そのため、陰性であったからといって必ずしも安心できるわけではありません。
また大腸に異常の無い健常者でも陽性になりますので、陽性であったからといって、確実に大腸がんというわけでもありません。便潜血陽性者のうちで、実際に大腸がんが発見される方は5%以下とされています。
ただし、大腸がんがない場合でも、潰瘍性大腸炎やクローン病など炎症性腸疾患で便潜血陽性となる場合がありますし、精密検査をきっかけに大腸ポリープが偶然に発見され、大腸がんの予防につながることもあります。大腸カメラ検査で自身のお腹の中がどうなっているかを確認するきっかけとして積極的に利用してください。
大腸カメラ検査
(大腸内視鏡検査)
 大腸カメラ検査は、肛門から、先端にカメラや照明、処置用の鉗子口などが付いた細いスコープを挿入し、大腸の粘膜を隅々まで観察することができる検査です。早期の大腸がんやポリープなどはエコー検査やX線検査では映りにくいことも多く、これらを確実に発見し、その位置や状態などをしっかりと観察し、さらにその場で生検検査や治療をすることができるのは大腸カメラ検査だけです。
大腸カメラ検査は、肛門から、先端にカメラや照明、処置用の鉗子口などが付いた細いスコープを挿入し、大腸の粘膜を隅々まで観察することができる検査です。早期の大腸がんやポリープなどはエコー検査やX線検査では映りにくいことも多く、これらを確実に発見し、その位置や状態などをしっかりと観察し、さらにその場で生検検査や治療をすることができるのは大腸カメラ検査だけです。
その上、疑わしい組織は採取して病理検査を行い、確定診断に結び付けたり、前がん病変である大腸ポリープを見つけたら、その場で切除し将来のがん化の予防に役立てたりすることもできる有効な検査です。
40歳以上の方は
大腸カメラ検査を
受けましょう
大腸がんは、早期のうちに発見すれば、内視鏡だけの簡単な手術で完治させることができるがんです。しかし、早期のうちにはまず自覚症状が現れません。
そのため、早期のうちに大腸がんを確実に発見するためには大腸カメラ検査が必須のものとなります。
大腸がんは40歳ごろから少しずつ罹患数が増え始め、50歳を過ぎると急激にその数が増加していきます。これは40歳頃から前がん病変である大腸ポリープが増えてくることにも関連があると考えられます。
そのため40歳を過ぎたら、まずは一度大腸カメラ検査を受けることをお勧めします。その後は状態によって医師の勧めるスケジュールで定期的に経過観察しましょう。
また、大腸がんの家族歴などがある場合は、30~35歳のうちにまずは検査を受け、その後は定期的な検査で自身の大腸の状態を確認しましょう。
おおの内科・内視鏡クリニックでは、消化器内科・内視鏡の専門医が丁寧でありながら、スピーディで身体に優しい大腸カメラ検査を行っておりますので、安心してご相談ください。
大腸がんのステージ
大腸がんに限らず、がんは現在、その進行度を現すステージという考え方が、その後の治療方針等の指針を立案するための基本的な分類となっています。 ステージを決定するには、がんの大きさ(T)、リンパ節への転移状態(N)、他の臓器への転移の有無(M)という3つの要素を組み合わせて0~Ⅳまでの5つのステージに分類していきます。 Ⅰ~Ⅳまでのステージはさらに、TNMの組み合わせによって、Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC、ⅢA、ⅢB、ⅢC、ⅣA、ⅣB、ⅣCの10段階に細分されています。 大腸がんと診断されると、検査によってステージを確定します。
ステージ0期
大腸の粘膜層にがん細胞が認められますが、リンパ節への転移は認められません。
この期であれば、内視鏡的な治療で完治が見込めます。
ステージⅠ期
- 大腸の粘膜下層~固有筋層までにがん細胞が認められますが、リンパ節への転移は認めらません。
ステージⅠ期はT因子で治療方針が異なります。
T1a
- 大腸の粘膜下層までにがん細胞が認められますが、浸潤距離は1000μm未満です。
- Ⅰ期でもこのサイズまでであれば、内視鏡的な治療だけで完治が見込めます。
T1b~T2
- 大腸の粘膜下層を1000μm以上浸潤しているか、固有筋層までがん細胞が認められます。
- Ⅰ期でもこのサイズの場合、開腹手術や腹腔鏡下手術などが行われます。再発率は6%と言われています。
ステージⅡ期
- リンパ節への転移や遠隔転移は認められませんが、がん細胞が固有筋層を超えて浸潤が認められます。
Ⅱ期の場合、いずれも開腹手術や腹腔鏡下手術などが行われます。再発リスクの高い場合に限って、術後に化学療法を継続することがあります。術後化学療法は6か月行うことが一般的です。再発率は15%と言われています。
ステージⅢ期
ステージⅢ期はA~Cにわけられています。それぞれ、いずれかの項目に該当する状態です。
ⅢA期
- がん細胞が粘膜下層まで拡がっており、リンパ節への転移は6箇所まで
- がん細胞が固有筋層まで拡がっており、リンパ節への転移が3箇所まで
ⅢB期
- がん細胞が粘膜下層までにとどまっていますが、リンパ節への転移が7箇所以上または主リンパ節まで転移しています。
- がん細胞が固有筋層から漿膜下層まで浸潤していて、リンパ節への転移は4~6箇所まで。
- がん細胞が漿膜表面に浸潤また漿膜を破って露出していますが、リンパ節への転移は1~3箇所まで。
ⅢC期
- がん細胞が固有筋層から漿膜下層までにとどまっていますが、リンパ節への転移が7箇所以上または主リンパ節まで転移しています。
- がん細胞が漿膜表面に浸潤また漿膜を破って露出していますが、リンパ節への転移は4~6箇所まで。
- がん細胞が直接多臓器に浸潤していますが、腹膜への転移は見られず、リンパ節への転移は1~3箇所まで。
Ⅲ期の場合、いずれも開腹手術や腹腔鏡下手術などが行われます。術後に化学療法を継続して行います。術後化学療法は6か月行うことが一般的です。Ⅲ期になると再発率は30%と可能性も高くなり、また予後の状態も良好とは言えないケースが増えてきます。
ステージⅣ期
ステージⅣ期もA、B、Cの3つの段階に分けられます。
ⅣA期
- がん細胞の大きさ、リンパ節転移に関わらず、腹膜以外の1臓器に遠隔転移を認めます。
ⅣB期
- がん細胞の大きさ、リンパ節転移に関わらず、腹膜以外の2臓器以上に遠隔転移を認めます。
ⅣC期
- がん細胞の大きさ、リンパ節転移に関わらず、腹膜に遠隔転移を認めます。
Ⅳ期では、他の臓器に転移したがん(遠隔転移巣)が切除できるかを判断します。
遠隔転移巣、原発巣はいずれも切除可能な場合は、手術が勧められます。
それ以外の場合には、化学療法、放射線療法などの手術以外の治療法が勧められます。
化学療法を行う場合、大腸がん組織の遺伝子検査を行い、その結果によって治療薬を選択します。
手術で切除できない場合でも薬物療法の効果があったときには、手術で切除できる場合もあります。
遠隔転移巣の切除が不可能かつ原発巣の切除が可能な場合で、原発巣による症状があるときなどは、原発巣の手術を勧められる場合があります。